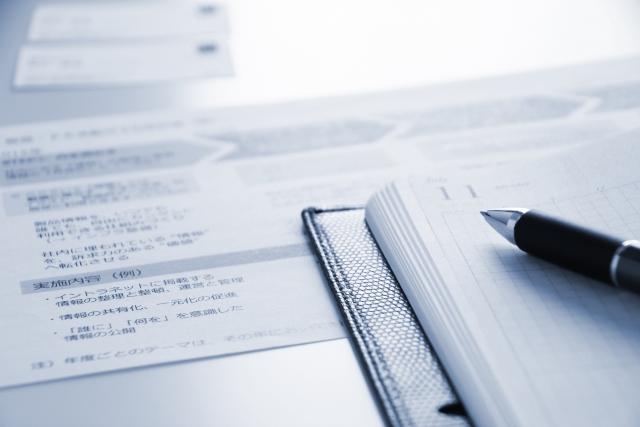社長が自分の給料を隠す会社は、社員が育たない!? 「オープンブックマネジメント」のススメ

社長のみなさんにお尋ねします。あなたは自分の給与の額を従業員に公表していますか? 業績についても包み隠さず、オープンにしているでしょうか? 今回は、「会社回りの数字を社員と共有すべし」と、私が考える理由について解説してみたいと思います。
「何も見えない」状態で、社員のお尻を叩いても効果ナシ……
――素朴な疑問なのですが、上場していない中小企業でも、業績などの会社の数字をオープンにすべきものなのでしょうか。業績が良い時はまだしも、悪くなると不安をあおるような気もして……。
五島 「うちの社員は危機感がなさすぎる」「当事者意識をもっと持ってほしい」――経営者からそんなグチを耳にすることがよくあります。
しかし、そのために何か施策を講じているかというと、「もっとがんばれ」と精神論のみに走っているようなケースも多い。
社員にとっては、何も見えない状態で「突っ走れ!」と、ただただお尻を叩かれているようなものです。
では、どうするか。当事者意識を持ってもらうには、自分&自社が立たされている状況を具体的に数値でクリアにすべし。「会社の数字は、みんなで共有しましょう」というのが私の考えです。
業績が低迷している時こそ、“悪い情報”を早めに共有すべし
五島 実際、アメリカで90年代、中堅企業の間で生まれた経営手法に「オープンブックマネジメント」というものがあります。
ブックとは会計帳簿や財務諸表のこと。会社の業績をオープンにし、自立型組織を作りましょうという考え方です。私も以前、本で読んだことがありますが、まさに我が意を得たりという思いでした。
とくに業績が悪くなると、「社員を不安にさせたくない」と数字を隠すような経営者も多いようですが、むしろ逆。どん底に落ちる前に、「悪い情報こそ、早めに報告するべし」が「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」の基本。
具体的な形で危機感を共有することで、“全員野球”で打つ手も見えてくるはずです。
さらに、「会社の数字」をクリアにしたら、それを「報酬」に連動させることが肝要。そのために、社長は自分の給与の額も堂々と公表すべきだと思います。

――自分の給与の額までとなると、抵抗感を覚える経営者が多い気がします。
五島 日本では、お金の話をタブー視する風潮が、まだまだ根強くありますが、業績の実態を明らかにした上で、社長自身の給与がいくらで、その額の根拠は何なのか。
そこもオープンにしなければ、社員の給料の額の根拠、報酬アップの仕組みもクリアにならないはずです。
実際、社員の給料については、「〇歳だから〇円ぐらいだろう」「世間並みに〇円ぐらい払えばOKだろう」と、“なんとなく”決めているケースも多いかもしれませんが、それではいくら「会社の数字をオープン」にしても、社員のモチベーションアップにはつながりにくい。
いい人材を獲得するためにも、昇給の仕組みをクリアにすべし
――社長の給料を公表すると、「社長だけたくさんもらって、自分たちは……」といった不満を生むケースもあるのでは?
五島 業績が良いときはそう感じる社員もいるでしょうが、業績が悪いときに真っ先に減らすべきは社長の給料です。さらに、借入の際には社長の個人保証をつけるなど、それだけリスクをとっているわけですから、業績が良いときに、社長の給料を高く設定するのは当然のことです。
そうしたことを、社員にもしっかり説明した上で、社員にも利益や成果に連動した報酬(インセンティブ)を支払われるような仕組みを作る。
私自身も、事務所のスタッフには、自分の給料を伝えた上で、「いくら欲しいのか」のリクエストを聞き、仕事をしていく上での目標やこちらの要望も具体的に伝えています。
――確かに、「会社の数字」と「自分の報酬」が連動した形でクリアになれば、社員のがんばり方も変わってきそうですね。
五島 不況で“買い手市場”だった一昔前ならまだしも、今後、本格的な人手不足の時代に突入するなか、給与や昇給の仕組みをオープンにする必要性はますます高まりを見せていくことでしょう。
いい人材を獲得し、業績につなげていくためにも、まずは“隠ぺい体質”を脱し、会社の数字の共有化を進めていくことをお勧めします。